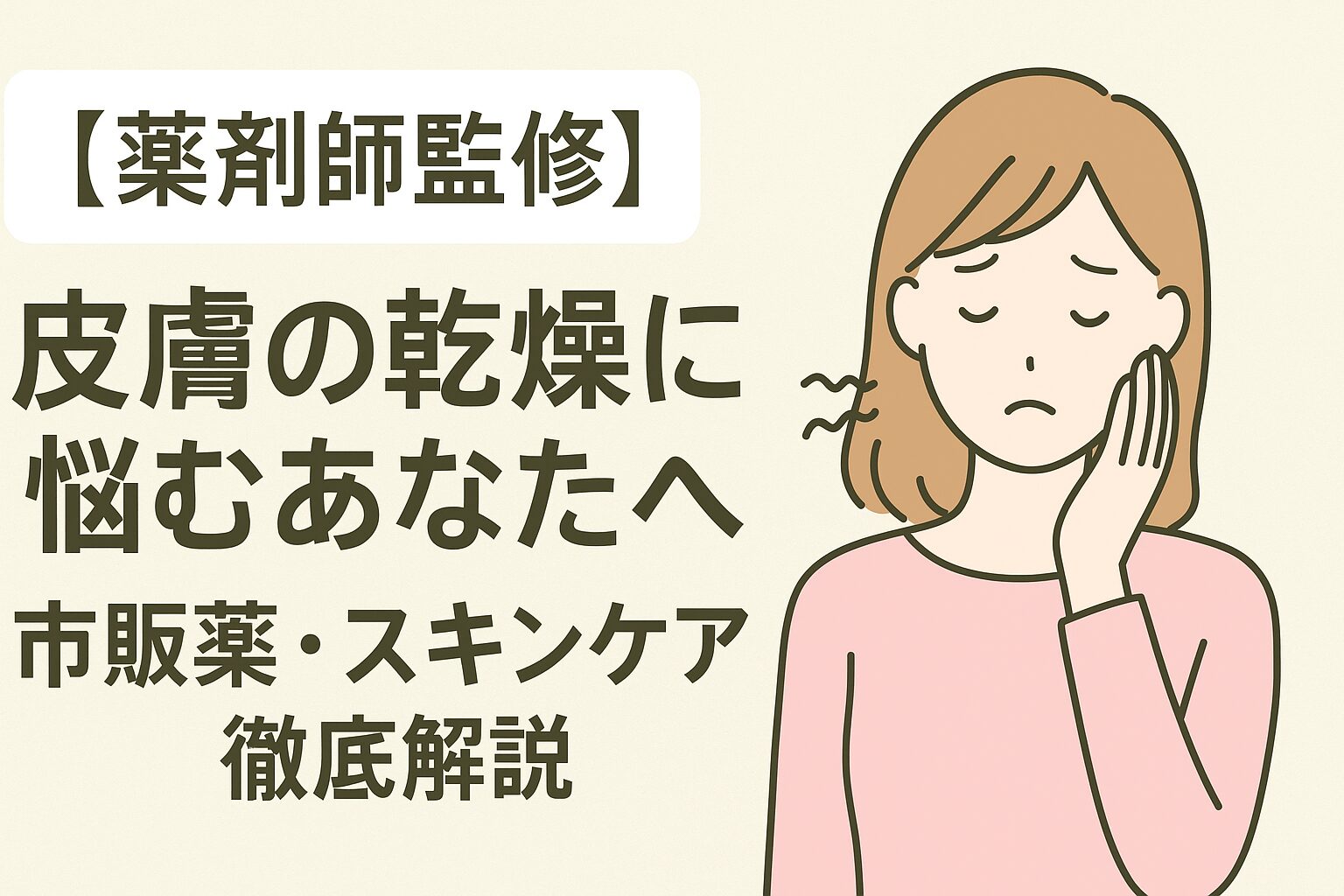冬場や季節の変わり目に「肌がかさつく」「かゆみが出る」「粉をふいたようになる」などのトラブルは、多くの方が経験します。乾燥は単なる美容上の問題だけではなく、バリア機能の低下によって湿疹や皮膚炎につながることもあります。
特に子供や高齢者は皮脂分泌が少なく乾燥しやすく、またアトピー性皮膚炎などの基礎疾患を持つ方は慢性的な乾燥に悩まされるケースも少なくありません。
本記事では 皮膚の乾燥の原因と考えられる疾患、市販で使える保湿剤・外用薬の選び方、成分解説、病院受診の目安 を薬剤師の視点で詳しく解説していきます。
皮膚乾燥の主な原因を徹底解説
皮膚乾燥(ドライスキン)は単なる「水分不足」ではなく、角質層のバリア機能低下や皮脂量の減少、外部刺激の影響など、複数の要因が関わっています。以下に代表的な原因を詳しく解説します。
季節要因(冬の乾燥、エアコンによる乾燥)
- 冬季の乾燥
気温が下がると皮脂の分泌量が減少し、さらに湿度の低下によって角質層の水分保持能力が低下します。その結果、肌の表面が白く粉を吹いたり、かゆみが出やすくなります。特に手・すね・顔など露出部に出やすいのが特徴です。 - エアコンによる乾燥
夏場の冷房・冬場の暖房は空気中の湿度を著しく下げます。オフィス勤務や長時間の室内滞在では、肌の水分蒸散が進み、乾燥によるつっぱりやかゆみが起こりやすくなります。
加齢による皮脂分泌・角質水分保持能の低下
- 皮脂腺・汗腺機能の低下
加齢に伴って皮脂や天然保湿因子(NMF)、セラミドの産生が減少します。そのため、若い頃は問題なかった環境でも乾燥が起きやすくなります。 - バリア機能の低下
角質層の水分保持機能が落ちることで外的刺激(衣服の摩擦、花粉、ほこり)に敏感になり、かゆみや湿疹を伴いやすくなります。
入浴習慣(熱いお湯・石けんの使いすぎ)
- 熱いお湯
42℃以上の熱い湯は皮脂を急速に洗い流し、肌表面の保護膜を奪います。入浴直後はしっとりしているように感じても、時間が経つと急激に乾燥してしまいます。 - 石けん・ボディソープの使いすぎ
強い洗浄成分を含む石けんは皮脂や保湿成分を過剰に除去します。毎日のゴシゴシ洗いは逆効果で、乾燥肌やかゆみの悪化要因となります。
疾患による乾燥
- アトピー性皮膚炎
角質層のセラミド欠乏によって皮膚のバリア機能が低下。乾燥に加え、炎症や強いかゆみが生じます。 - 糖尿病
高血糖状態が続くと、末梢血流障害や代謝異常により皮膚の水分保持能が低下。乾燥・かゆみ・感染リスクが高まります。 - 腎不全・肝疾患
代謝異常や体内の老廃物の蓄積が皮膚乾燥を悪化させます。かゆみを伴うことが多く、患者のQOLを著しく低下させます。 - 甲状腺機能低下症
代謝の低下により皮脂分泌が減少。全身の肌がカサカサになりやすく、顔色のくすみや浮腫も伴う場合があります。
乾燥肌ケアに用いられる成分と特徴
■ 保湿成分
- ヘパリン類似物質:血行促進・保湿・抗炎症作用。乾燥肌全般に第一選択される成分。
- ワセリン:皮膚表面に膜を作り、水分蒸散を防ぐ(ラップするイメージ)。刺激が少なく乳幼児にも使える。ただし、夏場など汗をかいたりすると、あせものようなことになることも。
- 尿素:角質をやわらかくし、水分保持を高める。かかと・ひじ・ひざの硬い部分に有効。ただし炎症部位では刺激になることも。
- セラミド:角層細胞間脂質を補い、バリア機能を強化。敏感肌の保湿に有効。
■ 炎症を抑える成分
- 低用量ステロイド外用薬(OTC):かゆみや赤みを伴う乾燥肌に短期間使用。
- 抗ヒスタミン成分配合外用薬:かゆみが強い場合に。

市販で買える乾燥肌対策アイテム(保湿剤・軟膏)
ヒルドイドローション類似品(ヘパリン類似物質含有製品)
- 成分:ヘパリン類似物質
- 特徴:医療用でよく処方されるヒルドイドと同等成分を含み、保湿+血行促進効果があります。乾燥肌の改善だけでなく、かゆみや軽い炎症にも有効。
- 使用感:サラッとした乳液タイプや、しっとり系のクリームタイプがあります。肌なじみがよく、ベタつきが少ない。
- おすすめポイント:粉ふきや乾燥によるかゆみがある人、敏感肌でシンプルな保湿剤を求める人に適しています。小児から高齢者まで幅広く使用可能。
ワセリン(白色ワセリン/プロペトなど)
- 成分:ワセリン(単一成分)
- 特徴:皮膚表面にバリアを作り、水分蒸発を防ぎます。添加物が少なく、赤ちゃんや敏感肌の方でも使いやすいのが魅力。
- 使用感:ややベタつきがあるものの、安全性が高く、リップや顔、手足などあらゆる部位に使えます。
- おすすめポイント:乳児や高齢者のスキンケアに安心。アトピーや敏感肌の方の「まず試すべき基本の保湿剤」。
尿素配合製剤(ケラチナミンクリーム、ウレパールクリーム)
- 成分:尿素
- 特徴:硬くなった角質を柔らかくし、水分を保持。特にかかと・ひじ・ひざなど「ゴワゴワ・ガサガサ」に強い効果を発揮します。
- 使用感:ややしっとりしており、重ね塗りしてもなじみやすい。部分ケアに最適。
- おすすめポイント:かかとのひび割れや魚の目の周辺、乾燥で硬くなった皮膚を改善したい人におすすめ。ただし顔や敏感部位には刺激になることがあるので注意。
セラミド配合保湿剤(キュレル、アトピスマイル)
- 成分:セラミド機能成分
- 特徴:皮膚の角質層に存在する「細胞間脂質」を補い、水分保持機能を強化します。肌のバリア機能を改善し、乾燥だけでなく外部刺激(花粉・紫外線・雑菌など)からも守ります。特に「ヒト型セラミド」は浸透性が高く、乾燥肌や敏感肌に効果的とされています。
- 使用感:クリームやローションに配合され、しっとり感が持続。ワセリンに比べるとベタつきが少なく、顔や全身に日常的に使いやすい。敏感肌用スキンケア商品に多く配合されています。
- おすすめポイント:アトピー性皮膚炎の補助ケアや季節性乾燥肌にも有効。赤ちゃんから高齢者まで安心して使いやすい。
季節ごとの乾燥対策
冬の乾燥対策
- 冬は湿度が低く、暖房でさらに乾燥が進むため、肌のバリア機能が低下しやすい季節です。
対策ポイント
入浴後はタオルでやさしく押さえるように拭き、3分以内に保湿剤を塗布
加湿器を使用して室内湿度を40〜60%に保つ
入浴は長湯を避け、38〜40℃程度のぬるめのお湯で10〜15分以内
夏の乾燥対策
- 夏は一見、乾燥しにくいように思えますが、汗や紫外線、エアコンによる乾燥が起こります。
対策ポイント
紫外線対策をしっかり行い、肌の炎症や水分蒸発を防ぐ
エアコン使用時は加湿器を併用
汗をかいたら強く拭かず、濡れタオルで軽く押さえる
年齢別の乾燥ケアポイント
乳児の乾燥ケア
- 赤ちゃんの肌はバリア機能が未熟で、水分保持力が低い
- ケアのポイント
- 入浴は短時間で石けんは低刺激なベビー用を使用
- 毎日保湿を習慣化(ローション・ミルク・クリームを部位ごとに使い分け)
- 特に口周りや関節部位は乾燥しやすいため、重点的に保湿
成人の乾燥ケア
- ストレスや生活習慣、紫外線、化粧品による刺激が乾燥の原因に
- ケアのポイント
- 保湿だけでなく、抗酸化ケア(ビタミンC・E)を意識
- 適度な睡眠・バランスの良い食事で肌の再生力を高める
- 季節に応じて保湿剤のテクスチャーを使い分け(夏はローション、冬はクリーム)
高齢者の乾燥ケア
- 加齢により皮脂分泌が低下し、角質が硬くなるため乾燥が強まる
- ケアのポイント
- 保湿剤は尿素・セラミド配合のクリームを中心に選ぶ
- かゆみが強い場合はメントール入りを避け、刺激の少ない保湿剤を選択
- 服薬(高血圧・糖尿病薬など)による乾燥も考慮し、医師・薬剤師に相談
セルフケアで取り入れたいOTC以外のお勧め商品
皮膚の乾燥対策は、外用薬や保湿剤だけでは不十分なこともあります。生活環境を整えたり、肌にやさしいアイテムを取り入れることで、乾燥をより効果的に防ぐことができます。ここでは、薬局や通販で手に入る OTC以外のセルフケア商品 を紹介します。
加湿器
- 冬やエアコン使用時の乾燥対策には必須アイテム。
- 室内湿度は 40~60%程度 が目安。乾燥しすぎると肌荒れやかゆみが悪化します。
- 超音波式・スチーム式などタイプがあるが、手入れが簡単なモデルがおすすめ。
保湿効果のある入浴剤
- 入浴は乾燥の大きな原因になり得ますが、保湿成分を含む入浴剤を使うことでお湯の刺激を和らげられます。
- 【注目成分】セラミド、ヒアルロン酸、オイル系成分(ホホバ油、スクワランなど)。
- 乾燥肌やアトピー傾向のある人向けに、無香料・低刺激タイプを選ぶのが安心です。
スキンケア家電(スチーマー)
- 蒸気を利用して肌に潤いを与える美容機器。
- 洗顔後や就寝前に使うと、化粧水や保湿クリームの浸透をサポートします。
- 特に乾燥の強い冬場や、加齢による乾燥が気になる方におすすめ。
保湿インナー・衣類
- 冬場の乾燥対策には、肌に直接触れる衣類選びも大切です。
- 綿素材やシルク混素材など、刺激の少ない肌着を選ぶと摩擦ダメージを減らせます。
- 最近は「保湿成分を繊維に加工したインナー」や「静電気防止加工」された衣類もあり、肌荒れ予防に役立ちます。
アロマオイル・植物オイル
- ココナッツオイル、ホホバオイル、アルガンオイルなどは乾燥肌ケアに人気。
- ただし顔や敏感部位に使用する際は、パッチテストを行うのが安心です。
- OTC外ですが、自然派ケアを好む方に選ばれる傾向があります。
病院にかかる目安と治療内容
次のような場合は市販薬ではなく皮膚科の受診が推奨されます。
- 強いかゆみ・赤みがある
- ジュクジュクしている、かさぶたができている
- 市販薬で2週間以上改善が見られない
- 全身に乾燥・かゆみが広がる
- 小児・高齢者で皮膚炎が悪化している
病院での治療内容
- 保湿剤(ヒルドイドローション、ビーソフテンなど)処方
- ステロイド外用薬(強さを調整して処方)
- タクロリムス軟膏(プロトピック)など免疫抑制外用薬
- 抗ヒスタミン薬(内服):かゆみが強い場合
病院とOTC、どちらが安い?
- OTC保湿剤:ヒルマイルドやケラチナミンなど → 1,000~2,000円程度
- 病院処方(保険適用):初診料+薬代で1,000~2,500円程度(3割負担)
Q&A よくある質問
Q1. 尿素クリームは子供に使えますか?
→ 高濃度尿素は刺激が強いため、子供には不向き。子供にはワセリンやヘパリン類似物質がおすすめ。
Q2. 保湿剤はいつ塗るのが効果的?
→ 入浴後3分以内がベスト。皮膚が少し湿っている状態で塗ると浸透しやすい。
Q3. ステロイド外用薬を自己判断で長く使っていい?
→ 長期連用は副作用リスクがあるためNG。必ず医師に相談。
Q4. 市販のヘパリン類似物質と処方薬ヒルドイドは違う?
→ 有効成分は同じ。ただし処方薬は保険適用で安価、OTCは自由に買えるメリットがある。
まとめ
- 皮膚の乾燥は「保湿+炎症対策」でコントロール可能
- 成分別に選ぶ(ワセリン=バリア、尿素=角質柔軟、ヘパリン類似=万能、セラミド=敏感肌)
- 軽度はOTCで、広範囲や重症は皮膚科へ
- 病院の方がコスパが良い場合も多い