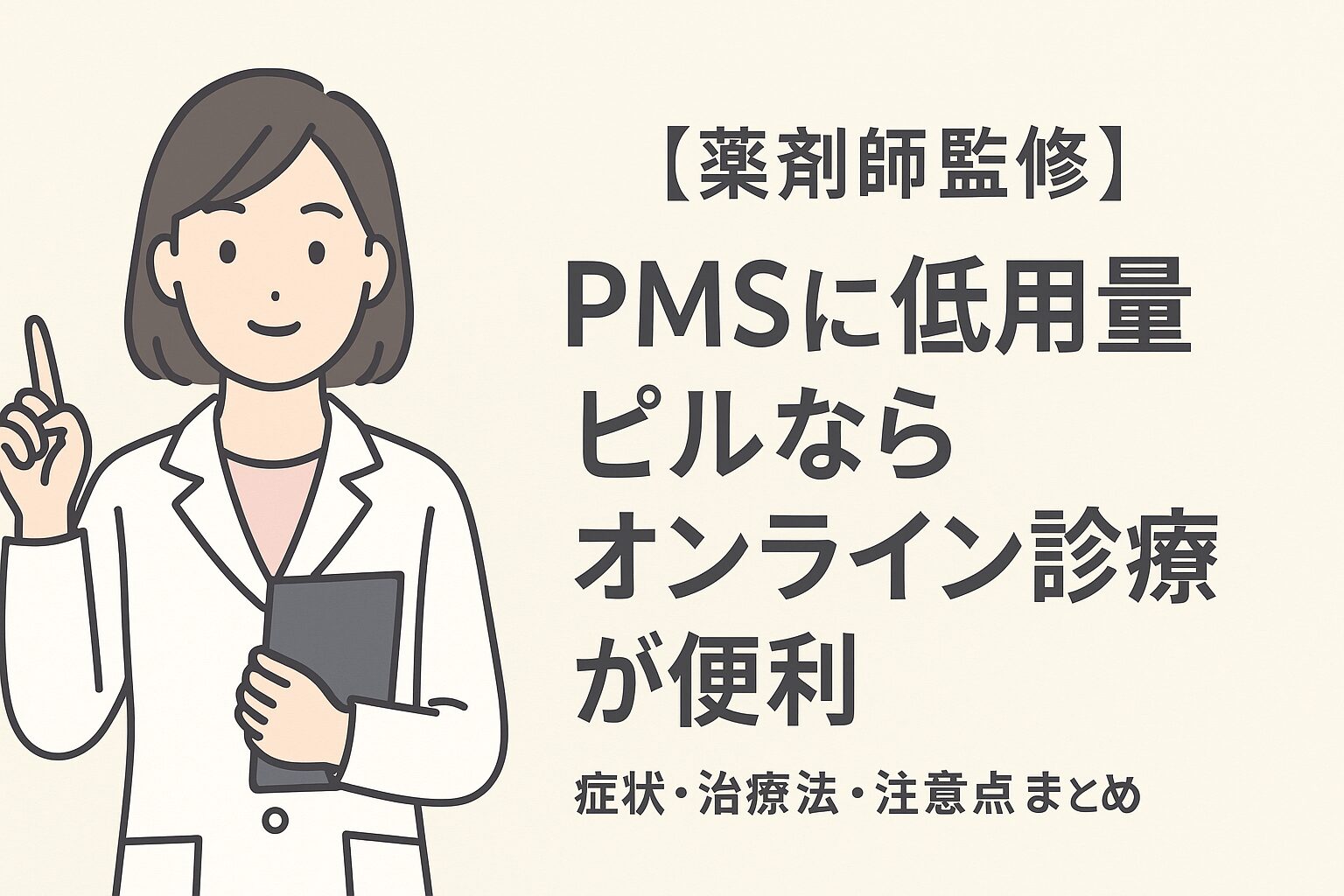「月経前になると気分が落ち込む」「頭痛やイライラで日常生活に支障が出る」――これは多くの女性が抱える PMS(月経前症候群) の典型的な症状です。
PMSはホルモンバランスの変動によって起こるため、生活習慣改善だけでは十分にコントロールできないことも少なくありません。
そんな中、近年注目されているのが 低用量ピルの服用 です。特に、オンライン診療を通じて自宅にいながら診察・処方を受けられる仕組みは、多忙な現代女性にとって強い味方となっています。
PMS(月経前症候群)とは?
主な症状
- 気分の落ち込み、不安感、イライラ
- 頭痛、腰痛、下腹部痛
- むくみ、乳房の張り
- 集中力低下、倦怠感
これらの症状は 月経の3〜10日前に現れ、生理が始まると軽減する のが特徴です。
原因
PMSは明確な「原因疾患」ではなく、 排卵後に分泌される黄体ホルモン(プロゲステロン)と卵胞ホルモン(エストロゲン)の変動 が関与していると考えられています。
PMSの治療法
PMSに対しては大きく分けて以下の治療が行われます。
- 生活習慣の改善
- 適度な運動
- 塩分・カフェイン・アルコールを控える
- 睡眠をしっかり取る
- 市販薬(OTC)による対処
- 漢方薬(加味逍遥散、抑肝散など)
- 鎮痛薬(頭痛や生理痛対策)
- 医療機関での治療
- 低用量ピル
- 抗不安薬や抗うつ薬(PMDDの場合)
低用量ピルがPMSに有効な理由
低用量ピルは「排卵を抑える」ことでホルモン変動を安定させ、PMSの症状を軽減します。
低用量ピルの働き
- 排卵を抑えホルモン変動を穏やかにする
- 子宮内膜を安定させ、月経痛も和らげる
- 月経量を減らし、貧血改善にもつながる
特に気分の変動や身体のむくみ・頭痛に悩む方には有効とされています。
ピルと関係するホルモンの違い
1. エストロゲン(卵胞ホルモン)
- 主に卵巣から分泌される女性ホルモン。
- 役割:子宮内膜を厚くして妊娠に備える、骨や血管・皮膚を健康に保つ、女性らしい体つきをつくる。
- ピルでは「エチニルエストラジオール」や「エストラジオール」が人工的に使われる。
- 多すぎると → 吐き気、乳房の張り、血栓症リスク。
- 少なすぎると → 出血コントロール不良、避妊効果の低下。
2. プロゲスチン(黄体ホルモン類似薬)
- 本来は「プロゲステロン」が自然の黄体ホルモン。ピルでは合成した「プロゲスチン」を使う。
- 役割:排卵を抑制、子宮内膜を安定化、頸管粘液を変化させて精子を通りにくくする。
- プロゲスチンは種類によって「アンドロゲン作用(男性ホルモン様作用)」の強弱が異なる。
- この違いが「ニキビ改善」や「体重増加」など副作用・効果の差につながる。
3. アンドロゲン(男性ホルモン)
- テストステロンなど、主に男性に多いホルモン。
- 女性の体にも少量存在し、性欲や体毛、皮脂分泌に関与する。
- ピルのプロゲスチンには「アンドロゲン作用を持つタイプ」と「アンドロゲン作用を弱めるタイプ」がある。
- → アンドロゲン作用が強いと:ニキビ・多毛・皮脂増加が出やすい。
- → アンドロゲン作用が弱い/抗アンドロゲン作用があると:肌荒れやニキビが改善しやすい。
ピルの世代ごとの違い(ホルモン作用との関連)
低用量ピルは、女性ホルモンのうち「エストロゲン」と「プロゲスチン」を配合した薬です。特に「プロゲスチン」の種類で世代が分けられています。
第1世代(ノルエチステロンなど)
- アンドロゲン作用がやや強め → ニキビや多毛が出やすい場合あり。
- 副作用(吐き気・浮腫)が比較的多かった。
- 現在は治療目的で一部使用(例:ルナベル)。
第2世代(レボノルゲストレル)
- アンドロゲン作用あり(やや強い)。
- 避妊効果と出血コントロールが安定しており、日本で最も処方される。
- 初めてピルを使う方によく選ばれる。
第3世代(デソゲストレル、ゲストデンなど)
- アンドロゲン作用が弱い/ほぼ中性。
- そのため ニキビ改善や多毛抑制 に効果が期待できる。
- ただし一部で血栓リスクが第2世代よりやや高いとされる。
- 美容目的+避妊で選ばれることが多い(例:マーベロン)。
第4世代(ドロスピレノン)
- 抗アンドロゲン作用+抗ミネラルコルチコイド作用 を持つ。
- むくみや体重増加を防ぎ、PMS改善に特に強い。
- 月経困難症やPMDDに対しても有効(例:ヤーズ)。
低用量ピルの21錠タイプと28錠タイプの違い
低用量ピルには大きく分けて 「21錠タイプ」 と 「28錠タイプ」 があり、いずれも含まれる有効成分(エストロゲン+プロゲスチン)は基本的に同じです。
しかし、錠数の違いによって 飲み方の流れ・飲み忘れのリスク・生活リズムへの影響 に差が出ます。
21錠タイプ
- 内容:ホルモンを含む錠剤が21錠のみ
- 飲み方:21日間連続して服用し、その後7日間は薬を飲まずに休薬する
- 生理(消退出血):休薬中の数日後に出血が始まる
- 特徴:
- シンプルで昔からある一般的なタイプ
- 「飲まない期間」があるため、飲み忘れやすい
- 自分で7日間の休薬を数える必要がある
28錠タイプ
- 内容:ホルモンを含む錠剤21錠+ホルモンを含まない錠剤(偽薬)7錠
- 飲み方:28日間毎日連続して服用し、飲み終えたら次のシートに移る
- 生理(消退出血):偽薬を飲んでいる間に出血が始まる
- 特徴:
- 飲み忘れを防ぎやすい(毎日「飲む」習慣がつく)
- 偽薬期間も錠剤を服用するため、リズムが一定
- 服薬管理がしやすく初心者に向いている
比較表
| タイプ | 内容 | 飲み方 | 出血のタイミング | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|
| 21錠タイプ | 有効成分入り21錠 | 21日間服用 → 7日間休薬 | 休薬中に出血 | 錠数が少なくコスパやや良い | 休薬管理が必要、飲み忘れやすい |
| 28錠タイプ | 有効成分入り21錠+偽薬7錠 | 28日間連続服用 | 偽薬中に出血 | 毎日飲む習慣ができ、忘れにくい | 偽薬分でやや価格が高め |
低用量ピルと選ぶポイント
ルナベル(Lunabell)
- 成分:ノルエチステロン(第1世代)+エチニルエストラジオール
- 特徴:月経困難症に対して保険適用。避妊よりは治療目的が中心
- 向いている人:月経痛が強い人、医療保険で安く使いたい人
トリキュラー(Triquilar)
- 成分:レボノルゲストレル(第2世代)
- 特徴:ホルモン量が段階的に変化する3相性ピル。自然なホルモン変動に近い
- 向いている人:出血量を減らしたい人、経血コントロールを重視する人
アンジュ(Ange)
- 成分:レボノルゲストレル(第2世代)
- 特徴:日本でよく処方される3相性ピル。安全性が高く、長年使用実績あり
- 向いている人:初めて低用量ピルを使う人
マーベロン(Marvelon)
- 成分:デソゲストレル(第3世代)
- 特徴:避妊効果に加え、ニキビや多毛の改善効果も期待できる
- 向いている人:PMS+肌荒れも気になる人
ヤーズ(Yaz)
- 成分:ドロスピレノン(第4世代)
- 特徴:月経困難症、PMS/PMDD改善で保険適用。むくみを改善する効果も
- 向いている人:PMS症状が重い人、むくみや体重増加が気になる人
避妊が主目的 → アンジュ、トリキュラー、マーベロン
PMSやPMDDの改善 → ヤーズ(第4世代)
月経困難症(生理痛が重い) → ルナベル、ヤーズ(保険適用あり)
肌荒れやニキビ改善も狙いたい → マーベロン(第3世代)
初めての方・安全性重視 → アンジュ、トリキュラー(第2世代)
低用量ピルの副作用と注意点
低用量ピルはPMSの改善や避妊効果に優れていますが、副作用が全くないわけではありません。安心して続けるためには「どんな副作用があり得るか」を知り、正しく対処することが大切です。
よく見られる副作用(服用初期に多い)
- 吐き気・胃の不快感 … 服用開始直後に出やすいが、数週間で落ち着くことが多い
- 不正出血 … 飲み始めて1〜3か月に見られるが、継続で自然に改善するケースが多い
- 乳房の張り・頭痛 … ホルモン変化による一時的なもの
まれに見られる重大な副作用
- 血栓症(肺塞栓症・脳梗塞など)
→ 息苦しさ、脚の腫れ、激しい頭痛、視力異常が出たらすぐ受診 - 肝機能障害
→ 黄疸、強い倦怠感が出たら服用を中止し受診
副作用が起きやすいリスク因子
- 35歳以上で喫煙している
- 高血圧・糖尿病・肥満など血管リスクがある
- 家族に血栓症の既往がある
副作用を避けるための工夫
- 服用開始前に医師の問診・血圧測定を受ける
- 定期的に血圧をチェックする
- 水分補給・長時間同じ姿勢を避ける
- 喫煙している方は禁煙を検討する
低用量ピルはどのくらいの女性が使っている?
日本での低用量ピルの使用率
- 日本で低用量ピル(経口避妊薬)が承認されたのは1999年と比較的遅めです。
- そのため利用率は他国と比べて低く、日本の15〜49歳女性のうち約3%程度にとどまっているとされています。
- 一方で、避妊目的以外に「月経困難症」「PMS」「子宮内膜症」など治療目的での処方も増えており、徐々に普及が進んでいます。
海外と比較した普及率
- フランスやドイツなど欧州諸国では、女性の30〜40%以上がピルを使用している国もあります。
- アメリカでも約15%前後と、日本の数倍にのぼります。
- 日本で低い理由としては
- 長年「避妊はコンドームが主流」だった文化的背景
- ピルに対する「副作用・太るのでは?」といった誤解
- 医師の診察が必要で入手がやや面倒
などが挙げられます。
最近の変化と利用が増えている
- 近年は「オンライン診療」で自宅から簡単に処方が受けられるようになり、利用者数が増加傾向にあります。
- SNSやWebメディアを通じて「避妊薬」だけでなく「生理痛やPMSを和らげる薬」として認知され始めている点も普及を後押し。
- 特に10〜20代の若い世代を中心に、婦人科受診のハードルを下げる動きが見られます。
オンライン診療で低用量ピルを処方してもらうメリット
近年は、スマホやパソコンを通じて診察・処方が完結する オンライン診療 が広まっています。
メリット
- 通院不要:自宅から診察が受けられる
- プライバシー保護:待合室で人目を気にしなくてよい
- 薬が自宅に届く:配送対応のサービスもあり便利
- 忙しい女性に最適:仕事や育児で時間がない人でも続けやすい
注意点
- 健康状態によっては服用できない場合もある
- 定期的に血液検査が必要なケースもある
- サービスごとに費用が異なる
病院 vs オンライン診療|どちらが便利?
| 項目 | 病院 | オンライン診療 |
|---|---|---|
| 利便性 | 通院が必要 | スマホで完結 |
| プライバシー | 人目が気になる | 自宅で完結 |
| 検査 | その場で血液検査可 | 提携クリニックで検査依頼 |
| 費用 | 保険適用外(3,000〜4,000円/月が目安) | サービスによって同程度 |
→ 初めての方や不安が強い方は「対面診療」、利便性を重視する方は「オンライン診療」がおすすめです。
おすすめは「ルナルナ オンライン診療」
生理管理アプリで有名な「ルナルナ」は、オンライン診療サービスも提供しています。特にPMSに悩む女性にとって使いやすい仕組みが整っています。
ルナルナの特徴
- 生理管理アプリと連動
→ 過去の生理周期データを活用して医師に正確に相談できる。 - 女性特化のオンライン診療
→ PMSやピル処方に強い医師と繋がれる。 - 自宅に薬をお届け
→ ピルを薬局に行かず受け取れる。 - 予約〜診療までアプリ完結
→ 忙しい女性でも隙間時間に受診可能。
Q&A|よくある質問
Q1. 低用量ピルは誰でも飲めますか?
A. 血栓症リスクの高い方や喫煙者、40歳以上の女性は注意が必要です。必ず医師の診察を受けてから服用してください。
Q2. 飲み忘れた場合はどうすればいいですか?
A. 服用時間を12時間以内に思い出した場合はすぐ服用。24時間以上過ぎた場合は医師・薬剤師に確認してください。
Q3. PMS以外のメリットはありますか?
A. 月経痛・過多月経・ニキビ改善・避妊効果などがあります。
まとめ
- PMSはホルモン変動が原因で、心身にさまざまな不調をもたらします。
- 低用量ピルはホルモンバランスを整え、PMS症状を軽減する有効な治療法です。
- オンライン診療なら通院不要で、プライバシーにも配慮しながら治療を続けられます。
- 特に「ルナルナ オンライン診療」は、生理管理アプリと連動していて便利で安心。
💡PMSに悩んでいる方は、まずはオンライン診療を活用して相談してみることをおすすめします。